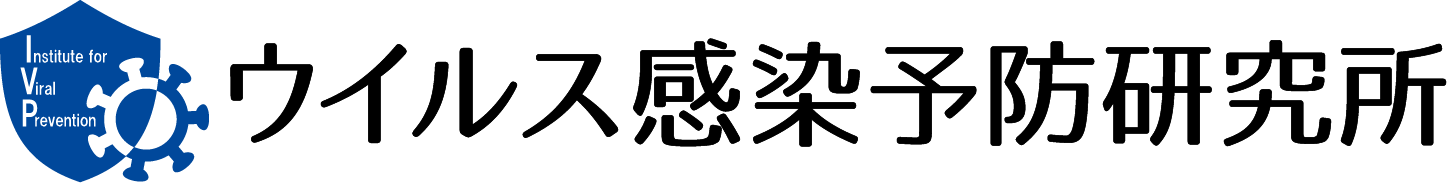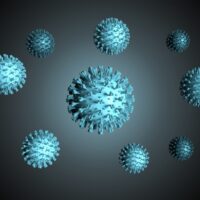大阪・関西万博

「大阪・関西万博」、正式名:2025年日本国際博覧会(Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan)、が大阪市此花区夢洲で開かれています。開催期間は2025年(令和7年)4月13日 – 10月13日の184日間です。この博覧会は、登録博覧会(登録博)に区分されており、総合的なテーマを扱う大規模博覧会として実施されるものです。大阪で開催されるのは登録博としては、あの1970年に吹田市で開催された日本万国博覧会以来55年ぶり2回目に当たるとのことです。開催までには、いろいろありましたが、いったん開催された以上、私としては、是非、みんなで盛り上げて、成功させたいと、一市民として思っています。
「大阪・関西万博」のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン(英語: Designing Future Society for Our Lives)」 で、これは、我々人類の共通したテーマですし、コンセプトも「– People’s Living Lab- 未来社会の実験場」です。事業費は、3,187億円、想定来場者数、2,820万人で、この人数を達成するには、毎日の平均入場者が15万人以上が必要とのことですから、是非、協力して達成させたいですね。私も浜松の生まれですが、今は、近くの京都に住んでいますので、是非、行ってみようと思います。私もウイルス研究を通して、細胞のこと、健康のことを考えていますので、興味深いテーマです。公式ロゴマークは、思いもつかない斬新なデザインで、命を持つ「細胞」をコンセプトにしているとのことで、大阪市のクリエータ、TEAM INARI(シマダタモツ氏代表)が創作しています。公式キャラクターの「ミャクミャク」も命を支える血液 (赤) と水 (青)を基調とした一目で分かるキャラクターで、作者は、神戸市育ち、県立明石高校、大阪芸大美術学科卒の絵本作家、山下浩平氏とのことで、関西にかかわりがあると同時に、いずれも、いのちの輝きを表現しており、発展的に世界の人に愛着が持てるものになっていると思います。
オフィシャルテーマソングは、関西発のコブクロが歌う 「この地球(ほし)の続きを」で、これがとても良いです。作詞、作曲は、小渕健太郎・黒田俊介両氏、編曲はコブクロです。知らなかったのですが、コブクロの名前は、小渕と黒田に由来しており、大阪府堺市の路上で音楽活動をしていた2人が出会って結成されたとのことです。特に、出だしの「2025 未来見に行こう!当たり前に 空を飛べる 100年先を想像できるかい?」、最後の、「子供達が変えてゆく この地球(ほし)の続きを 2025 未来見に行こう!」が、コブクロの澄んだ声量のある歌声と共に、子供を含めた合唱がマッチして、さらに言えば、「こんにちは」というフレーズの繰り返しが、55年前、三波春夫さんと子供たちが歌った、テーマソング「世界の国からこんにちは」と呼応、連携があり、しかも楽曲として進化しており、曲に合わせたダンスも考えられていて、とても良いです。夏には、この歌とおどりで盆踊りもできます。特に、7人の子供たちが、55年まえの万博のシンボルであった、芸術家・岡本太郎氏の「太陽の塔」の前に広がる緑の草原で、青空のもと、コブクロの圧倒的な歌声、楽曲に合わせて、存分に手足を伸ばして躍動するダンスが良いです。サイトは下記です。
コブクロ、万博テーマソング
この歌で、100年先がどうなるのかという趣旨のフレーズが出てきます。話は飛びますが、インフルエンザウイルスは、100年先でも、地球上に存在し、毎年、インフルエンザの流行があり、インフルエンザパンデミックは起きるのでしょうかと素朴に思います。私は、このままいけば、インフルエンザウイルスは、100年先でも存在し、季節性インフルエンザの流行、さらに世界に広がるインフルエンザパンデミックは起こる可能性があると考えています。勿論、テクノロジーは進化し、ウイルスのサーベイランス、ワクチン、抗ウイルス薬などの開発技術は飛躍的に良いものになることは確実で、患者数は、それに伴い減っていきます。しかし、一方で、人類は、常に、SDGsに代表される持続的な目標を掲げています。即ち、貧困、飢餓や不平等、気候変動、環境劣化の防止、健康、福祉、産業、技術革新、繁栄、平和と公正の推進などですが、その中で、特に、人類は、豊かな自然との調和を目指しており、野生動植物と人類の共生・共存を実行しています。この中で、極めて変異しやすいインフルエンザウイルスなどを選択的に根絶することは、容易なことではありません。多くのウイルスは、自然界では、常に変異、進化を遂げており、周りの環境に順応したものが選択され、残されて行くからです。従って、野生動植物との共生・共存方法は正しく着実に行う必要があります。